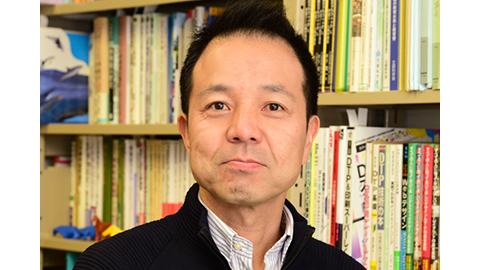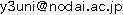|
職名 |
教授 |
|
研究室住所 |
北海道網走市八坂196 |
|
研究室電話 |
0152-48-3857 |
|
連絡先 |
|
|
ホームページ |
|
|
外部リンク |
|
|
宇仁 義和 (ウニ ヨシカズ) UNI Yoshikazu 教授 |
学内職務経歴 【 表示 / 非表示 】
-
東京農業大学 生物産業学部 准教授
2006年04月 - 2021年03月
-
東京農業大学 教職・学術情報課程 学術情報課程 准教授
2006年04月 - 現在
-
東京農業大学 生物産業学部 教授
2021年04月 - 現在
所属学協会 【 表示 / 非表示 】
-
全日本博物館学会
2010年06月 - 現在
-
日本セトロジー研究会
2005年06月 - 現在
-
「野生生物と社会」学会
2016年01月 - 現在
-
日本民具学会
2024年11月 - 現在
-
北海道民族学会
2012年04月 - 現在
論文 【 表示 / 非表示 】
-
民俗資料の収集と廃棄の基準を議論するための事例紹介 査読あり
宇仁義和・本間浩一・持田誠・石井淳平
博物館学雑誌 50 ( 2 ) 2025年04月
-
Uni Yoshikazu, Torstein Sjøvold
Japan Cetology 35 ( 0 ) 9 - 17 2025年
担当区分:筆頭著者 記述言語:英語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:The Cetology Study Group of Japan
The diary offers a detailed account of his voyage to Vladivostok via the Suez Canal accompanied by two whale-catchers, Nikolai and Georgy. Subsequently, he constructed a whaling station in Gaydamak, near Vladivostok, which is now part of Nakhodka City. The whaling station, which employs personnel from Japan, China, Korea, and several other countries, constitutes the focal point for whaling operations spanning the Russian Far East and the Korean Peninsula. The diary records the number and species of whales captured by the company. From the description of the diary, Walby was employed by a Japanese whaling company to supervise the construction of a whale-catcher in Osaka and to participate in whaling operations as a gunner in the Sea of Japan, from the Tsushima Strait to the Korean Peninsula, and off Kagoshima Prefecture in southern Kyushu. The diary indicates that he visited a hot spring in Unzen and the ancient capital Nara from Osaka, during the period of unemployment, prior to his contract with a Japanese whaling company. A review of the diary entries and articles in fishing journals of the same period revealed that Walby started working as a gunner in 1899 for a Japanese whaling company, a year later than the descriptions of Akashi (1910) and Tønnessen (1967). Nevertheless, Walby was the first gunner of a modern Japanese whaling company to be recorded and the first to hunt a whale with a whaling cannon. The value of Walby’s diary lies in its detailed internal record of whaling companies, which makes it an invaluable source of information on the earliest days of modern whaling, from the Russian Far East to the Korean coast, and to Japan at the end of the 19th century.
-
公立博物館の設置主体の可能性と運営形態の多様性 査読あり
宇仁義和・持田誠
博物館学雑誌 50 ( 1 ) 2024年12月
担当区分:筆頭著者
-
韓国の学芸員制度と博物館:日本との比較から 査読あり
宇仁義和・オンゼウォン
博物館学雑誌 49 ( 2 ) 2024年04月
-
2023年4月施行の改正博物館法に向けた議論の検証と法的課題 査読あり
宇仁義和・持田誠・石井淳平
博物館学雑誌 49 ( 1 ) 2023年12月
書籍等出版物 【 表示 / 非表示 】
-
歴史的自然としての海洋―日本近海の海獣類と猟業史
池谷和信、宇仁 義和ほか14名( 担当: 共著 , 範囲: 168-189)
世界思想社 2010年03月
記述言語:日本語
日本近海の海獣類についての分布と歴史的認識を概説し、近代日本の海獣猟業と個体群への影響にふれた。
-
自然ガイド知床
宇仁 義和( 担当: 単著)
北海道新聞社 2007年07月
記述言語:日本語
世界自然遺産に登録された知床の自然を豊富な写真で幅広く紹介したガイドブック
-
水と自然遺産
秋道智彌編、宇仁 義和( 担当: 共著 , 範囲: 67-78)
小学館 2007年03月
記述言語:日本語
歴史的視点から知床の自然を分析し、保全のあり方を考えたもの
-
斜里町史第三巻
宇仁義和( 担当: 共著 , 範囲: pp.162-166,233-238)
斜里町 2004年11月
記述言語:日本語
担当部分:淡水魚・鯨類
3回目となる町史の自然編に執筆.内容は知床博物館での斜里川水系幾品川の淡水魚分布調査と漂着鯨類調査の結果.
執筆者は知床博物館学芸員を中心に8人.
B5版.1242ページ
MISC 【 表示 / 非表示 】
-
ローカル情報をアカデミアにつなぐ 招待あり
宇仁義和
勇魚 80 2024年12月
-
身体で感じる授業が記憶に残る:教育の未来を語る Tea Room No. 84
宇仁義和
北海道通信日刊教育版 126894 2024年06月
-
メディアが取り上げた野生生物と人との関わりを検証する:野生生物管理におけるメディアとのつきあい方
宇仁義和
Wildlife Forum 26 ( 1 ) 2021年08月
-
トド・アザラシの漁業被害との共存 招待あり
宇仁義和
BIOSTORY 30 2018年12月
-
東洋捕鯨樺太事業場跡を探して
宇仁義和
セトケンニューズレター 37 2016年12月
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
「民俗資料」の収集保存基準と検索名称の開発:工場部品から日記まで
2023年04月 - 2026年03月
基盤研究(C) 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
-
鳥獣と家畜のあいだ―近代日本の毛皮産業と牽引力
2018年04月 - 2021年03月
基盤研究(C) 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
-
明治大正期に遡る一次資料「事業場長必携」を用いた東洋捕鯨の操業復元
2014年04月 - 2017年03月
基盤研究(C) 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
-
もうひとつの近代鯨類学「第一鯨学」の形成と展開
2011年04月 - 2014年03月
基盤研究(C) 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
-
アイヌ文化における捕鯨の検討
2003年04月 - 2004年02月
奨励研究(B)
担当区分:研究代表者
その他競争的資金獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
地方における生涯教育で学芸員制度が果たしてきた機能と役割の検証―韓国との比較から
2022年09月 - 2023年12月
北野生涯教育振興会研究助成
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
-
ネットワーク型学芸員の活動アーカイブの作成と価値評価
2016年10月 - 2017年09月
全国大学博物館学講座協議会(全博協)東日本部会研究助成
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
-
イギリス博物館の連携と支援の現地調査および実践としての共有データサイトの構築
2011年10月 - 2012年09月
全国大学博物館学講座協議会(全博協)東日本部会研究助成
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
-
地方博物館の評論とその教材化
2009年10月 - 2010年09月
全国大学博物館学講座協議会(全博協)東日本部会研究助成
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示 】
-
Past Feeding Ground, Migration route and new records of the Western Gray Whale off Japan 国際会議
宇仁 義和
International Union for Conservation of Nature 2008年09月
開催年月日: 2008年09月
記述言語:英語 会議種別:口頭発表(一般)
the Western Gray Whale Rangewide Workshop, Tokyo.
-
Review of Catch Records of Marine Mammals in Japanese Waters 国際会議
宇仁 義和
Marine Mammals of the Holarctic 2006年09月
開催年月日: 2006年09月
記述言語:英語 会議種別:口頭発表(一般)
4th International Conference "Marine Mammals of the Holarctic", St. Pertersburg. Russia. (全北区海生哺乳類学会議).サンクト・ペテルブルク.ポスター発表.
-
日本のアザラシ毛皮産業はいかに成立したか 国際会議
宇仁 義和
生き物文化誌学会 2006年06月
開催年月日: 2006年06月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
生き物文化誌学会第4回学術大会.網走.
-
地方博物館の独自機能~競合施設との比較から 国際会議
宇仁 義和
日本ミュージアム・マネージメント学会 2006年05月
開催年月日: 2006年05月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
日本ミュージアム・マネージメント学会第11回大会.東京.
-
Ice-entrapment of Killer Whales in the Sea of Okhotsk 国際会議
Aota Masaaki, Tateyama Kazutaka、宇仁 義和
The society for Marine Mammalogy 2005年12月
開催年月日: 2005年12月
記述言語:英語 会議種別:口頭発表(一般)
The 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, San Diego(海生哺乳類学会議).サンディエゴ.ポスター発表.
担当経験のある科目(授業) 【 表示 / 非表示 】
-
森林資源機能論
機関名:東京農業大学
-
博物館実習
機関名:東京農業大学
-
博物館経営論
機関名:東京農業大学
-
博物館情報・メディア論
機関名:東京農業大学
-
博物館展示論
機関名:東京農業大学
その他教育活動及び特記事項 【 表示 / 非表示 】
-
アイヌと海の哺乳類:先住民族の森川海に関する権利4ー海とアイヌ民族.さっぽろ自由学校「遊」森川海のアイヌ先住権研究プロジェクト.札幌
2024年05月
-
網走の捕鯨100年:クジラの街で再出発するには 網走青年会議所5月第1例会「郷が有する文化の古今から、郷への知見を広げよう」.網走
2024年05月
-
問題提起「あふれかえる民俗資料の未来」 横浜フォーラム2023「フランスから考える民俗資料の収集保存と活用方法」.横浜
2023年10月
-
北海道のミンク養殖業の歴史と歴史への影響.夏季企画展特別講演会.サケのふるさと千歳水族館.千歳
2022年08月
-
博物館法改正議論をフォローする学習会.北海道博物館協会学芸職員部会研修会.オンライン
2021年08月
委員歴 【 表示 / 非表示 】
-
網走市美術館協議会委員
2008年09月 - 現在
団体区分:自治体
-
網走開発建設部「河川水辺の国勢調査」アドバイザー
2009年06月 - 現在
団体区分:政府
社会貢献活動 【 表示 / 非表示 】
-
(公財)知床財団理事
2024年06月 - 現在
-
(NPO法人)サーモン・サイエンス・ミュージアム監事
2023年07月 - 現在
-
全国大学博物館学講座協議会(全博協)東日本部会会長校・事務局
2023年10月 - 2025年09月
メディア報道 【 表示 / 非表示 】
-
放送100年特集 食べることは生きること「きょうの料理」誕生秘話 テレビ・ラジオ番組
2025年03月
-
オホーツク文化期から連なる網走の捕鯨
北海道情報誌HO 2024年08月
執筆者:本人以外
情報提供と取材対象
-
米国へ送られたクジラの頭骨 新聞・雑誌
日本経済新聞社 ナショナル ジオグラフィック 2018年09月
-
集団座礁したシャチを解剖 新聞・雑誌
日本経済新聞社 ナショナル ジオグラフィック 2005年05月