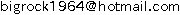|
Title |
Professor |
|
Laboratory Address |
東京都世田谷区桜丘1-1-1 |
|
Laboratory Phone number |
81-3-5477-2268 |
|
Laboratory Fax number |
81-3-5477-2267 |
|
Contact information |
|
|
Homepage |
|
|
External Link |
|
|
UEHARA Iwao Professor |
From School 【 display / non-display 】
-
Tokyo University of Agriculture Faculty of Agriculture Graduated
1983.04 - 1988.03
Country:Japan
-
Michigan State University Faculty of Agriculture Department of Forestry Others
1986.03 - 1987.03
Country:Japan
From Graduate School 【 display / non-display 】
-
Gifu University Graduate School, Division of Agricltural Sciences Doctor Course Completed
1997.04 - 2000.03
Country:Japan
-
Shinshu University Graduate School, Division of Agriculture Master Course Completed
1995.04 - 1997.03
Country:Japan
Studying abroad experiences 【 display / non-display 】
-
1986.03 - 1987.04 Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Michigan State University Exchange Program Student
Employment Record in Research 【 display / non-display 】
-
Tokyo University of Agriculture Junior College Department of Environment and Landscape Docent
2001.04 - 2002.03
-
Tokyo University of Agriculture Docent
2004.06 - 2006.09
-
Tokyo University of Agriculture Faculty of Regional Environment Science Department of Forest Science Associate Professor
2006.10 - 2011.03
-
Tokyo University of Agriculture Faculty of Regional Environment Science Department of Forest Science Professor
2011.04
External Career 【 display / non-display 】
-
金沢林業大学校 非常勤講師
2024.04
Country:Japan
-
みえ森林林業アカデミー 非常勤講師
2019.04
Country:Japan
-
兵庫県立森林大学校 非常勤講師
2018.04
Country:Japan
-
Michigan State Univeristy Faculty of Agriculture, Department of Forestry Professor
2017.08 - 2017.10
Country:United States
-
愛媛大学大学院農学研究科 非常勤講師
2006.04 - 2007.03
Country:Japan
Professional Memberships 【 display / non-display 】
-
日本数理生物学会
2015.01
-
関東森林学会
2011.10
-
中部森林学会
2011.10
-
日本森林保健学会
2010.04
-
応用森林学会
2006.10
Qualification and License 【 display / non-display 】
-
日本カウンセリング学会カウンセリング心理士(旧名:認定カウンセラー)
-
Practical English Proficiency Test (1or semi-1 or 2 class)
-
Hazardous Material Handler (second kind)
-
High School Teacher Specialization License
Papers 【 display / non-display 】
-
Shoko Toda and Iwao Uehara
Journal of Agriculture Science, Tokyo University of Agriculture 70 ( 2 ) 20 - 25 2025.09
Authorship:Last author Language:Japanese Publishing type:Research paper (bulletin of university, research institution)
Summary: Cuttings are a method of asexual propagation that uses plant parts. Since survival and rooting rates vary depending on various factors, such as the condition of the cuttings and differences in soil, it is necessary to consider a specific method for making cuttings to obtain a high survival rate. Hinoki (Chamaecyparis obtusa) is one of the main tree species planted for timber in Japan, and because the rooting rate varies between cultivars, we wondered if there is a way to improve the rooting rate by adjusting the cuttings. Two experiments were conducted using Hinoki. First, the cuttings were made to the same length of 16, 8, and 5 cm, and all the cut ends at the base were cut back into an oval shape. The survival rate and growth volume were lower at 5 cm than at 16 and 8 cm, respectively. Next, an experiment was conducted in which the shape of the cut was changed using scissors. Four shapes were prepared: cut back, diagonally, horizontally, and horizontally with a scratch on the top of the cut. The survival and growth rates were higher when the scissors were inserted at an angle, but no roots were observed when the scissors were inserted horizontally. Based on these findings, we believe that the optimal method for survival and growth is to cut cuttings to 8 cm or longer and to recut the base into an oval shape. In this study, cuttings were grown under different conditions, but it is possible that the survival rate and growth of cuttings can be improved by combining these conditions or using rooting promoters in combination.
Key words:cutting length, cut shape, survival rate, rooting rate, Hinoki cypress(Chamaecyparis obtusa) -
Therapeutic effects of forest bathing on older adult patients with essential hypertension: evidence from a subtropical evergreen broad-leaved forest Reviewed International coauthorship International journal
Aibo Li, Yu Liu, Haiyuan Qian, Kun Sun, Ziging Zhao, Iwao Uehara, Guofu Wang, Banzhi Zhou
Frontiers in Public Health 13 1 - 12 2025.07
Language:English Publishing type:Research paper (scientific journal) Publisher:Frontiers
Introduction: Forest bathing (Shinrin-Yoku) has gained growing attention in medical and therapeutic tourism research due to its potential benefits in managing chronic diseases, such as hypertension. This empirical study examined the therapeutic effects of forest bathing on older adult patients with essential hypertension.
Methods: A total of 36 participants were randomly assigned to either a forest environment (experimental group, n = 24) or an urban setting (control group, n = 12) for a three-day, two-night intervention. To minimize potential confounding factors, both groups followed identical dietary regimens, leisure activities, and sleep schedules throughout the intervention. Physiological and psychological assessments, including vital signs, inflammatory markers, heart rate variability (HRV), and mood states, were conducted at baseline and post-intervention.
Results: The results indicated that systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), and high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) levels were significantly lower in the experimental group compared to the control group (p < 0.05). Frequency domain parameters of HRV, specifically LF and the LF/HF ratio, significantly increased in the experimental group (p < 0.05). Additionally, psychological assessments revealed that participants exposed to the experimental group had significantly better emotional well-being. Specifically, tension-anxiety scores decreased significantly, while vigor-activity scores increased (p < 0.05).
Discussion: These findings suggest that forest bathing can serve as an effective non-pharmacological intervention for reducing blood pressure, improving autonomic function and mental health among older adult patients with essential hypertension. This study provides empirical evidence supporting the therapeutic potential of forest environments, particularly subtropical broad-leaved evergreen forests, in the integrated management of cardiovascular and mental health. -
An attempt at "Forest-Welfare Collaboration" in Kyushu's mountain forests Reviewed
Iwao UEHARA
Journal of Forest and Human Health Promotion Research 6 5 - 14 2025.06
Authorship:Lead author Language:English Publishing type:Research paper (scientific journal) Publisher:The Society of Forest Amenity and Human Health Promotion in Japan
Abstract:
There is a term called "agricultural welfare collaboration." This term refers to the collaboration and cooperation between agriculture and welfare. So, is there a term for forestry and welfare, or forests and welfare, a "forest welfare collaboration"? Forest environments have the effects and functions of health and relaxation, and scenic beauty, and forests offer a variety of amenities, including beautiful scenery, fragrances, and wild vegetables. Collaboration, cooperation, and fusion between forests, forestry, and welfare may seem intimidating, but perhaps it is something that can actually be done in our everyday lives. In this report, we will introduce an example of "forest welfare collaboration" in the mountain forests of Yame City, Fukuoka Prefecture.
Keywords: forest therapy, occupational therapy, forest recreation, intellectual disabilities, developmental disabilities -
Iwao UEHARA
Kanto Journal of Forest Research 76 ( 1 ) 29 - 32 2025.03
Authorship:Lead author Language:English Publishing type:Research paper (scientific journal) Publisher:関東森林学会
要旨:2011年3月の東日本大震災の発生以来,福島県内の各地にはいまなお放置された状態の山林が数多く存在している。本論文では,放射性降下物の汚染が甚大であった地域の一つである相馬地方のスギ,ヒノキの放置林および広葉樹二次林を対象地とし,それぞれ間伐をおこない,その後の植生回復を観察し,今後の当地における施業について提言することを目的とした。研究の方法は,各調査林分において50%の本数間伐を2019年~2022年に実施し,間伐前後の相対照度を比較し,それぞれ10 m×10 m(1a)の調査区を4か所ずつ設けて,2024年6~10月に植生調査をおこなった。各林分では30~50樹種前後の実生が見出されたものの,その上長成長は低く,スギ,ヒノキ林分においては林床の被覆度も低かった。その主な理由には林冠閉鎖による低照度が推察され,追加の間伐が必要と考えられた。
キーワード:相対照度,林床植生,被覆度,実生,50%間伐 -
Effects of leaf allelopathy on plant seedling growth of forest trees. Reviewed
Mai MARUYAMA, Megumi TANAKA, Iwao UEHARA
Kanto Journal of Forest Research 76 ( 1 ) 77 - 80 2025.03
Authorship:Corresponding author Language:Japanese Publishing type:Research paper (scientific journal)
Abstract: The plants have been reported to have allelopathic effects that inhibit or promote the growth of other plants. Although it is known that there are several pathways for their expression, such as volatilization and dissolution, few studies have focused on the allelopathic effects of trees, and also few have been able to identify the allelopathic substances. This study aimed to investigate the inclination and factors of allelopathic effects at six forest tree species, and to accumulate basic data. Growth indicators of lettuce
seedlings due to volatilization and leached components were measured. The results showed that although growth suppression was observed overall, there were no differences among species. The difference between fresh and defoliated leaves also differed among tree species. The growth inhibition in the Sandwich method may be due to the action of relatively stable substances.
Keywords: Allelopathy, Sandwich method, Dish pack method, Forest tree
Books and Other Publications 【 display / non-display 】
-
森林生態系の保全管理 -森林・野生動物・景観- Reviewed
小池孝良・上田裕文・梶 光一・宮本敏澄 編( Role: Contributor , 第12章5節コラム(pp.213~215)、第12章6節(pp.215~218))
共立出版 2025.09 ( ISBN:978-4-320-05848-4 )
Total pages:238 Responsible for pages:213~218 Language:Japanese Book type:Scholarly book
森林生態系のもたらすサービスとしては、その名の通り、生物多様性などの生態系サービスが中心である。しかし、福祉や医療面でのサービスについても考えられないだろうか?
農業と福祉の連携,協働では,「農福(のうふく)連携」という言葉がすでにある。高齢者施設や障害者施設の方々が田畑や農地に出かけて,野菜や草花、作物を育てる。そんな取り組みがその代表例である。農業と福祉は親和性が高く,その歴史も長い。その基盤には,植物と人間の親和性,相性の良さがあり、さらにその根底には、農作業の中には、リハビリテーションや療育の効果などが共存していることも作用している。
それでは,森林と福祉の「森福連携」はどうだろうか?例えば,丸太の剥皮や種子採集,シイタケづくり、山菜採りなどの作業は幼児から高齢者まで取り組むことができる。森林にはもとより保健休養や風致の効果,作用がある。その景観をはじめ,芳香や山菜など様々なアメニティも存在している。そしてさらに、医療との連携はいかがだろう?森林と地域医療との関係である。この場合は、「森医(しんい)連携」という関わりになるだろう。
本書では、その「森福連携」「森医連携」のこころみについて担当、執筆した。 -
Terapi Hutan dalam Konteks Malaysia Reviewed
Keeren Sudara Rajoo( Role: Supervisor (editorial))
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 2025.09 ( ISBN:978-983-49-5023-1 )
Total pages:115 Language:Malay Book type:General book, introductory book for general audience
マレーシアのプトラ大学の演習林における森林療法の方法についてのガイドブック。各手法について指導、監修した。
-
Iwao UEHARA( Role: Sole author)
2023.04 ( ISBN:978-4-88694-524-2 )
Total pages:207 Language:Japanese Book type:General book, introductory book for general audience
-
Silviculture Workbook How to practice Forest Science Reviewed
Iwao UEHARA( Role: Sole author)
2023.03 ( ISBN:978-4-8446-0928-5 )
Total pages:215 Responsible for pages:全頁 Language:Japanese Book type:Textbook, survey, introduction
-
ひらひら ふさふさ 花のカタチ みつけた!自然のかたちシリーズ3
上原 巌(原作、監修)、佐藤直樹(絵)、栗山 淳(構成)( Role: Supervisor (editorial))
農山漁村文化協会 2023.03
Total pages:36 Responsible for pages:全文 Language:Japanese Book type:General book, introductory book for general audience
2020年9月~2021年4月まで、東京農業大学 食と農の博物館にて開催した「自然の中の数学 展」の展示内容から、回転対称体など、数学的要素を含めて花の形について、絵本で紹介した。
Misc 【 display / non-display 】
-
上原 巌
東京農大 東日本支援プロジェクト 2025年度 成果報告書 1 ( 1 ) 8 - 9 2026.01
Authorship:Lead author Language:Japanese Publishing type:Rapid communication, short report, research note, etc. (bulletin of university, research institution) Publisher:東京農業大学
1.はじめに 相馬地方の放置林での間伐による植生再生
東京農業大学・東日本支援プロジェクトでは、2019年から相馬地方森林組合に作業委託をし、各地の私有林において間伐を実施してきた。2019年10月は相馬市今田地区のスギ林(36年生:立木密度3000本/ha、平均樹高11m、平均DBH 20㎝)、2020年12月には南相馬市原町区のヒノキ林(32年生:立木密度3500本/ha、平均樹高12m、平均DBH 15㎝)、2021年12月には相馬市玉野地区のコナラ、クリ等を主林木とする広葉樹二次林(立木密度3500本/ha、平均樹高17m、平均DBH 25㎝)、2022年12月には南相馬市小高区のヒノキ若齢林(約20年生:立木密度2000本/ha、平均樹高8m、平均DBH 14cm)において、それぞれ50%の強度間伐を実施した。間伐をおこなった結果、各林分の相対照度は向上し、新生の樹木の実生が確認されてきている。
そこで、本年度は、ここまでの間伐の成果をまとめるために、広葉樹二次林と2か所のヒノキ林において、福島県内の森林・林業関係者による現地研修会を実施するはこびとなった。
2.現地研修会の実施
現地研修会は、福島県森林組合連合会を通して9月より参加者を公募し、10月15日(水)に実施した。
研修会の参加者は、福島県森林組合連合会、相馬地方森林組合、地元の山林所有者の方をはじめ、南会津の木材生産者、いわき市の山林所有者などであった。
当日は、朝10時にJR福島駅前に集合し、乗用車に分乗して現地に向かった。午前から順番に、相馬市玉野地区の広葉樹林二次林(2021年に間伐実施)、南相馬市小高区の20年生のヒノキ林(2020年に間伐実施)、南相馬市原町区の20年生のヒノキ林(2022年に間伐実施)の3つの林分を踏査し(写真2)、18時半にJR福島駅で解散した。
現地研修会では、各林分の植生回復状況なども踏査したが、最も林床植生が繁茂したのは、広葉樹二次林であった。コナラ、クヌギ、モミなどの高木層の下に、50種以上の樹木の実生が確認された。次に若齢のヒノキ林では40種ほどの樹木の芽生えが見られ、その繁茂状況も旺盛であった(写真3)。漏脂病や徳利病などの病害も見られず、順調な成育がうかがえている。
研修会では、下記の事柄についても山林所有者の方からお聞きした。
①今から60~70年前は、上流からの水の便が良く、あちこちに水田を作ったが、震災後、稲作をやめてしまった農家が多い
②山林は地域の共有地であり、適地適木で分割されたものの、今ではその境界があいまいになってしまっている
③浜通り地方では、林木の年輪の目が細かいことから、かつては船材も生産していた。
④丸太は、馬や木馬を使って搬出をしていた
⑤現在では山主であっても、林床の樹木、植物がわからない
いずれもお聞きして有意義なことばかりであったが、山林における水利やかつての搬出の形態、また、造林種や、浜通りにおける立木の生育特性などについてもこれまで知らなかった知見を得ることができた。また、林床の樹種名がわからないとのことから、今後は、林地における樹木名の実地講習会もおこなうことが起案された。
福島県浜通り地方に限らず、とかく閉塞感、先行き不透明感のある森林・林業界であるが、間伐後に一斉に芽生えた植生のように、新たな希望を引き続き見つけていきたい。
3.今後の森林施業
スギ、ヒノキ林では、今後さらに追加間伐が必要であると思われる。とりわけヒノキ林の場合は、日光を遮る独特の樹冠が形成されるため、単純な本数による間伐率よりも、実際の林冠、樹冠の適正な配置による密度コントロールの方が重要である。当面は、この間伐の実施によって、林冠および林間の空間を開け、風散布、鳥散布などを、また埋土種子の発芽を促していくことが得策であると考える。植生的には、クリ、コナラ、ミズナラなどのブナ科をはじめ、ホオノキ、コブシ、カエデ類などの有用広葉樹が数多くみられており、貴重種のメグスリノキやクロモジなどの薬木もみられることから、これらの有用広葉樹の育成にも力点を注いでいくことが望まれる。林床に発現したこれらの実生の育成をおこない、針広混交林の造成とともに、林床植生の有効活用をはかることも今後の課題である。
4.訪問型農学スクールの実施
本年度は、相馬高校(7月)、相馬農業高校(11月)、原町高校(12月)の3校を訪問し、各学校において身近な樹木の観察、自然に中にみられる数学的要素、そして学校周辺で採集した樹木の枝葉から芳香水の製作をおこなった。 -
上原 巌
現代林業 715 1 - 6 2025.12
Authorship:Lead author Language:Japanese Publishing type:Rapid communication, short report, research note, etc. (scientific journal) Publisher:全国林業改良普及協会
東京農業大学では、2011年3月に「東日本支援プロジェクト」を立ち上げ、震災被害の把握をはじめ、農地、農業生産の再生、復興のお手伝いをさせていただいてきた。森林・林業関係では、福島県浜通り地方の森林における被害状況の調査を振り出しに、森林再生の支援をさせていただいてきている。2019年4月からは、国の「福島県イノベーション・コースト事業」の助成も受け、震災後に放置されていた浜通り地方の森林の間伐にも取り組んできた。間伐は50%の強度間伐をおこない、その前後における林内照度や林床植生の変化などについても、定点調査をおこなっている。今回、一つの区切りとして、間伐を実施した広葉樹二次林と2つのヒノキ林にて、福島県森林組合連合会を通して参加者を募り、見学会を実施する運びとなった。
見学会は、令和7年10月15日(水)におこなわれた。福島県森林組合連合会、相馬地方森林組合、地元の山林所有者の方をはじめ、南会津の木材生産者、いわき市の山林所有者などもご参加された。
当日は、朝10時にJR福島駅前に集合し、乗用車に分乗して現地に向かった。午前から順番に、相馬市玉野地区の広葉樹林二次林(2021年に間伐実施)、南相馬市小高区の20年生のヒノキ林(2020年に間伐実施)、南相馬市原町区の20年生のヒノキ林(2022年に間伐実施)の3つの林分を踏査し、18時半にJR福島駅で解散した。
見学会では、各林分の植生回復状況なども踏査したが、最も林床植生が繁茂したのは、広葉樹二次林であった。コナラ、クヌギ、モミなどの高木層の下に、50種以上の新たな樹木の実生が確認された。ヒノキ林でも30~40種ほどの樹木の芽生えが見られたが、その林地での被覆面積や植生高は、広葉樹二次林の半分以下だった。しかしながら、漏脂病や徳利病などのヒノキは見られず、順調に成育をしている。
研修会では、今から60~70年前、どの地域も上流からの水の便が良く、あちこちに水田を作ったが、震災後、稲作をやめてしまった農家が多いこと、山林は地域の共有地であり、適地適木で分割されたものの、今ではその境界があいまいになってしまったこと、浜通り地方では年輪の目が細かいことから、かつては船材も生産していたこと、丸太は、馬や木馬を使って搬出をしていたことなども山林所有者からお聞きした。
また、現在では山主であっても、林床の樹木、植物がわからないということをお聞きし、それは意外であった。そのことからも、次回は、林地における樹木名の実地講習会をおこなう予定である。
福島県浜通り地方に限らず、とかく閉塞感、先行き不透明感のある森林・林業界であるが、間伐後の植生のように、新たな希望の芽生えを引き続き見つけていきたい。 -
大学における受託研究の事例 Reviewed
上原 巌
森林技術 993 24 - 27 2025.11
Authorship:Lead author Language:Japanese Publishing type:Article, review, commentary, editorial, etc. (scientific journal) Publisher:日本森林技術協会
「開かれた大学」、「産官学連携」など、社会と連関した大学の研究活動は以前よりさらに推進され、加速化してきている。それは地域おこし、地域振興などをはじめ、新たな技術開発や新商品開発といった、ブレークスルーを必要とされる分野において、より活発な傾向にある。
農学系の分野においては、品種改良、収量増加や省力化によるスマート農林業、農林産物のマーケティングなど、より効率的な農林産物の生産を目的に、企業や団体が大学と社会連携をむすぶケースが多い。科学研究費においても、社会からのニーズを融合した研究が数多く見られる。
それでは、森林関係での産官学の連携はいかがだろうか?SDGを基盤とした林産物の生産、山村の再生、高層の木造建築、樹木の新たな機能の開発等があげられるだろう。
本報では、そのような社会連携活動の中で、大学の中にいわば「お助け窓口」的な受け皿を作り、社会からの相談や依頼を受け、研究をおこなっている事例を報告した。 -
<連載>森林と健康 森林浴、森林療法のいま 第36回 福岡県の地域病院における森林療法の実践ワークショップ Invited
上原 巌
森林レクリエーション 462 ( 1 ) 8 - 15 2025.11
Authorship:Lead author Language:Japanese Publishing type:Article, review, commentary, editorial, etc. (scientific journal) Publisher:一般社団法人 全国森林レクリエーション協会
福岡県北九州市小倉の西野病院および同病院の森林における森林療法のワークショップの実践の内容を報告した。
-
上原 巌
現代林業 713 1 - 6 2025.10
Authorship:Lead author Language:Japanese Publishing type:Rapid communication, short report, research note, etc. (scientific journal) Publisher:全国林業改良普及協会
幼少期、少年少女期の自然体験の重要性はかねてから指摘されている。ボーイスカウト、ガールスカウトも、その活動の基本は自然体験にある。自然科学系のノーベル賞の歴代授賞者でも、自然の中で遊びながら育ったという例は数多い。世界的、歴史的な科学研究の源は、自然環境、自然体験にあるのだ。では、21世紀の日本のこどもたちの自然体験は今どうなっているのだろう?今回は、関東のある小学生対象のワークショップの様子を紹介した。
Works 【 display / non-display 】
-
弟子屈・川湯温泉 アカエゾマツの森 ガイドマップ
摩周湖観光協会、上原 巌、萩原寛暢
2023.03
北海道・弟子屈町のアカエゾマツの天然林でのガイドマップを作製した。
-
心身を回復に導く「森林療法」
2014.05
森林浴と森林療法との違い、森林療法の実践事例、日本における今後の可能性などについて報告した。
-
森へ出かけませんか? -森の香り、緑の風景、川の音などを楽しもう
2014.05
森林浴の心身に対する効果についてまとめた
-
みどりの癒し (その29 森林美学)
上原 巌
2013.09
Work type:Artistic work Location:世田谷クオータリー
-
みどりの癒し (その28 古代ギリシャのヒポクラテス)
上原 巌
2013.07
Work type:Artistic work Location:世田谷クオータリー
Other research activities 【 display / non-display 】
-
造林樹木学ノート 第1章 スギ YouTube 動画
2021.07
「造林樹木学ノート」(コロナ社 2021)の第1章スギの写真を動画で紹介した。
-
造林樹木学ノート 第12章 林地でよくみる樹木 YouTube 動画
2021.07
「造林樹木学ノート」(コロナ社 2021)の第12章 林地でよくみる樹木の写真を動画で紹介した。
-
造林樹木学ノート 第11章 薬用樹木 YouTube 動画
2021.07
「造林樹木学ノート」(コロナ社 2021)の第11章 薬用樹木の写真を動画で紹介した。
-
造林樹木学ノート 第10章 特用樹木 YouTube 動画
2021.07
「造林樹木学ノート」(コロナ社 2021)の第10章 特用樹木の写真を動画で紹介した。
-
造林樹木学ノート 第9章 カエデ YouTube 動画
2021.07
「造林樹木学ノート」(コロナ社 2021)の第9章カエデの写真を動画で紹介した。
Honours, Awards and Prizes 【 display / non-display 】
-
2020.06 Japan Forest Technology Association Pioneer studies and dissemination activities of forest therapy utilized local forests
Iwao UEHARA
Award type:Award from Japanese society, conference, symposium, etc. Country:Japan
-
2024.07 日本カウンセリング学会
Award type:Award from Japanese society, conference, symposium, etc. Country:Japan
日本カウンセリング学会大会継続発表賞は、7年間のうち5回発表することが条件となっている。
2018年、2019年、2021年、2022年、2023年の5回の発表があり、受賞要件を満たし、今回の受賞となった。
2001年に本賞は創設され、第1回目より4回目の受賞である。 -
日本カウンセリング学会 大会発表継続賞
2016.08 日本カウンセリング学会
上原 巌
Award type:International academic award (Japan or overseas) Country:Japan
-
日本カウンセリング学会 大会発表継続賞
2008.11 日本カウンセリング学会
上原 巌
Award type:Award from Japanese society, conference, symposium, etc. Country:Japan
-
日本カウンセリング学会 大会発表継続賞
2001.11 日本カウンセリング学会
上原 巌
Award type:Award from Japanese society, conference, symposium, etc. Country:Japan
Scientific Research Funds Acquisition Results 【 display / non-display 】
-
Clinical studies on PTSD cares utilizing local forest environment
2005.04 - 2007.03
Grant-in-Aid for Scientific Research Sprout Research
Authorship:Principal investigator
Other External Funds 【 display / non-display 】
-
高齢者の森林空間活用による保健休養活動の促進のための普及啓発活動の展開
Grant number:7公A-25 2025.07 - 2026.06
国土緑化推進機構 令和7年度 緑と水の森林ファンド
三浦雄一郎、全国森林レクリエーション協会
Authorship:Coinvestigator(s) Grant type:Competitive
Grant amount:\1000000
山村地域資源としてポテンシャルを持った文化的・自然的資源の現状と山村地域資源の新たな活用方法を調査検討し、森林空間の活用の有効性の提示と利用者の拡大を図る。
(1)高齢化の進んだ山村地域における森林空間活用の現状把握。
(2)地域に存在する伝統文化、風土、風景、居住空間、有用・薬用植物の調査とそれらの新たな活用方法の開拓。
(3)山村地域居住者及び福祉事業関係者等に向けた未活用資源の有効活用の推進のためのフォーラムを開催。
(4)調査研究及びフォーラムの報告書を作成し、関係者に配布。 -
高齢化の進んだ山村の地域資源である森林空間と有用植物の新たな活用に関する調査
2022.07 - 2025.06
国土緑化推進機構 森林活用
三浦雄一郎、全国森林レクリエーション協会
Authorship:Coinvestigator(s) Grant type:Competitive
山村地域資源としてポテンシャルを持った文化的・自然的資源の現状と山村地域資源の新たな活用方法を調査検討し、森林空間の活用の有効性の提示と利用者の拡大を図る。
(1)高齢化の進んだ山村地域における森林空間活用の現状把握。
(2)地域に存在する伝統文化、風土、風景、居住空間、有用・薬用植物の調査とそれらの新たな活用方法の開拓。
(3)山村地域居住者及び福祉事業関係者等に向けた未活用資源の有効活用の推進のためのフォーラムを開催。
(4)調査研究及びフォーラムの報告書を作成し、関係者に配布。 -
障がい者・高齢者の保健休養活動及びレクリエーションによる 森林空間利用促進事業
2022.07 - 2025.03
農林水産省 森林活用
全国森林レクリエーション協会、日本森林保健学会
Authorship:Principal investigator Grant type:Competitive
障がい者や高齢者のための森林空間を利用した保健休養及びレクリエーションのプログラム実施に向けて、対象となる森林の環境条件、介助者等の人材育成、サービス提供体制支援策等をモデル的に実践し、各地の森林での普及を目指す。
-
東京農大:復興から地域創生への農林業支援プロジェクト
2021.06 - 2026.03
公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構
渋谷住男、山﨑晃司、中島亨、大島宏行、足達太郎、半杭真一
Authorship:Coinvestigator(s) Grant type:Competitive
(上原 巌担当分)
1)森林環境回復(地域環境科学部森林総合科学科 教授)
相馬地方の森林は、福島第一原発の事故後、特に放射性降下物質の濃度や放射線量が高いことがこれまでに報告されてきており、林業および林産物の活用は依然として停滞を強いられている。そこで本事業では、林業の主幹である人工造林の針葉樹(スギ、ヒノキ、マツ類など)を主な対象とし、それらの林分におけるモニタリングをおこないつつ、天然更新による広葉樹との針・広混交林を造成して、相馬地方及び福島における森林再生の一モデルを提示することを目的とする。
具体的には、相馬地方の複数樹種の森林において間伐を実施し、放置された森林の新陳代謝をはかるとともに、間伐後の林床における天然更新樹種の調査を行い、それらの樹種の導入から針・広混交林の造成に導き、相馬地方及び福島における森林再生の一モデルを提示していく。また、相馬地方の「津島マツ」などの郷土種の保存と育成もおこなう。間伐作業は、相馬地方森林組合に委託し、連携した森林再生を行う。
(2021年度 実施予定)
①相馬市において2019年に間伐を実施したスギ林の林床植生の調査をおこなう。
②南相馬市において2020年に間伐を実施したヒノキ林の林床植生の調査をおこなう。
③南相馬市の放置マツ林(民有林)または広葉樹二次林における間伐を実施し、同林における放射線量測定および採集サンプルの放射性降下物質の測定をおこない、間伐前後における林床照度や植生変化を調査する。 -
森林を活用した障害者の保健休養およびレクリエーションの今後の展開方向に関する実証的調査事業
2019.07 - 2022.12
一般財団法人 日本森林林業振興会
上原 巌、日本森林保健学会
Authorship:Principal investigator Grant type:Competitive
(1)全体事業計画書
1 事業の背景と目的
障害者を含むすべての人々が同等に生活し活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念に基づき、障害等の有無にかかわらず国民の誰もがその人格と個性を尊重し、支え合う「共生社会」の実現が求められている。
このような社会背景の中、2020年(令和2年)に身体障害者(肢体不自由(上肢・下肢および欠損、麻痺)、脳性麻痺、視覚障害、知的障害)を対象とした世界最高峰の障害者スポーツの総合競技大会であるパラリンピックが東京で開催されることとなった。1998年(平成10年)の長野パラリンピック冬季大会の際にも同様の現象がみられたが、同大会の開催を契機に一般の障害者スポーツへの関心が現在再び急速に高まりつつある。この機運を障害者全体への理解へと繋げ、さらにノーマライゼーションの普及、定着をはかっていくことが東京パラリンピックの開催趣旨、ミッションとしても重要な意義を持っている。そして、障害者への理解が深化したノーマライゼーション社会の実現のためには、様々な分野、機会を通じて必要な措置を講ずる努力をしていくことが重要である。
さて、森林は、木材生産をはじめ、災害防止、水源涵養、生物多様性の保全など、様々な機能を有しているが、近年はその保健休養機能として、森林浴や森林療法など、人々の健康増進をはじめ、医療、福祉においてもその活用が広がり、高まりをみせている。また、近年では、トレイルラン、マウンテンバイクなど、郊外の森林環境を活用したアウトドア・スポーツもその人気を高めている。しかしながら、前述したノーマライゼーション社会の実現のためには、障害等の有無にかかわらず、すべての人が森林を活用し、その保健休養効果やスポーツ、レクリエーションを享受できる環境・施設整備や、利用プログラム・ソフトの開発、そしてそれらをサービス・供給する体制の構築および人材面を育成することが課題である。
そこで、本事業では、わが国における障害者の森林活用の現状を調査分析するとともに、諸外国における状況と比較検討も行い、わが国における課題を抽出して、今後の展開方向をまず検討する。次に、森林の活用が障害者に及ぼす影響等を調査し、障害者が保健休養やスポーツ、レクリエーションの場として、その積極的な利用のために必要とする施設の整備や、効果的な利用プログラムを開発するとともに、その活動を支援する人材育成および体制づくりを検討する。これらの検討を通じて、障害者の森林を活用した保健休養および森林レクリエーション、スポーツの普及を図ることを目的とする。
2 事業の具体的内容
(1)わが国における障害者の森林活用の現状調査
ア 森林林公園等における障害者対応の状況
障害者が保健休養やレクリエーションとして森林公園等を利用するに当たっては、健常者とは異なったニーズや視点に立った施設整備や利用プログラムが必要となる。そこで、障害者の森林活用の実態を把握するため、全国の主要な森林公園(レクリエーションの森を含む。)の管理者等に対しアンケートにより、障害者の利用状況、障害者に対応した施設の整備状況、障害者が利用できるプログラムの有無と内容を調査する。
また、そのアンケート結果をふまえ、先進的な事例・モデル等を調査する。
イ 各アクティビティにおける障害者対応の現状
森林での休養、散策、スキー、ツリークライミング等、森林を活用した保健休養、レクリエーションにおける障害者対応の現状について、それらを企画運営している事業者等にヒアリング等を行い、障害者の参加の実態を把握し、先進的な事例・モデル等を調査する。
(2)森林における障害者への対応の諸外国の現状調査
障害者が森林での保健休養やレクリエーション活動を行うために必要な施設整備のガイドライン等について諸外国での整備状況の文献調査を行うとともに、障害者の利用・参加の先進的な優良事例を収集する。
(3)森林での保健休養やレクリエーションが障害者に及ぼす影響調査
障害者(特に知的障害者を主体として)が森林での保健休養やレクリエーション活動、アクティビティを行うことによって、どのような効果、作用があるかを調査し、障害別(レベルを含む)と森林環境条件のそれぞれの収集を行う。
(4)森林活用プログラムの開発
障害者が森林を活用した保健休養やレクリエーションを行うためには、施設の整備とともに、そのプログラムが必要となる。このため、上記(1)から(3)までの調査結果を踏まえ、障害の種類、レベルに応じた森林活用プログラムを開発する。
(5)ワークショップの開催
森林レクリエーションエリアに障害者をモニターとして招待し、保健休養やレクリエーションを体験していただき、これらの活動を支援する体制づくり、人材養成を検討するとともに、今後の展開方向についての課題を抽出する。
(6)シンポジウムの開催
“森林パラレクリエーション”の普及を目的としたシンポジウムを開催し、障害者にも対応した森林レクリエーションエリアにおける施設整備の促進と障害者の森林の保健休養、レクリエーション活用を支援する仕組みづくりの必要性の認識の普及を図る。
3 期待される波及効果
障害者のさらなる森林利用の拡大と促進、森林活用におけるノーマライゼ―ションのさらなる普及拡大に寄与することが考えられる。また、健常者に対しても、森林の保健休養、レクリエーションの選択肢が広がり、質の高いサービスの提供が可能となることが予想される。
(2)申請年度事業実施計画書
(1)わが国における障害者の森林活用の現状調査
①森林林公園等における障害者対応の状況調査
障害者の森林活用の実態を把握するため、全国の主要な森林公園(レクリエーションの森を含む。)の管理者等に対しアンケート調査を行い、障害者の利用状況、障害者に対応した施設の整備状況、障害者が利用できるプログラムの有無と内容を把握する。また、そのアンケート結果をふまえ、先進的な事例・モデル等も把握する。
②各アクティビティにおける障害者対応の現状
森林での休養、散策、スキー、ツリークライミング等、森林を活用した保健休養、レクリエーションにおける障害者対応の現状について、それらを企画運営している事業者等にヒアリング等を行い、障害者の参加の実態を把握し、先進的な事例・モデル等を調査する。
(2)森林における障害者への対応の諸外国の現状調査
障害者が森林での保健休養やレクリエーション活動を行うために必要な施設整備のガイドライン等について諸外国での整備状況の文献調査を行うとともに、障害者の利用・参加の先進的な優良事例を収集する。
(3)森林での保健休養やレクリエーションが障害者に及ぼす影響調査
障害者(特に知的障害者を主体として)が森林での保健休養やレクリエーション活動、アクティビティを行うことによって、どのような効果、作用があるかを調査し、障害別(レベルを含む)と森林環境条件のそれぞれの収集を行う。
(4)ワークショップの開催
森林レクリエーションエリアに障害者をモニターとして招待し、保健休養やレクリエーションを体験していただき、これらの活動を支援する体制づくり、人材養成を検討するとともに、今後の展開方向についての課題を抽出する。
Past of Commissioned Research 【 display / non-display 】
-
東京農業大学との富士市有林施業および利活用方法に係る調査研究
2024.04
静岡県富士市 一般受託研究 The General Consignment Study
上原 巌
Authorship:Principal investigator
Grant amount:\470000
-
針葉樹人工林の針広混交林化への造林支援及びに森林土壌の水質等に関する研究
2024.04
EPEJ株式会社 一般受託研究 The General Consignment Study
上原 巌
Authorship:Principal investigator
Grant amount:\220000
①飯能市大字北川に取得した森林 6.6ha の森林及び周辺の協力者の森林を対象にした針葉樹人工林の針広混交林化への造林支援
②造林支援期間の森林土壌の水質及び高麗川の水質の実態調査 -
世界農業遺産地域における放置里山林の再生をめざす「薬草・薬木図鑑」作成のための連携・協働による実践研究とその応用
2023.07 - 2024.03
大分県農林水産部農林水産企画課 世界農業遺産推進班 世界農業遺産 The General Consignment Study
上原 巌
Authorship:Principal investigator
Grant amount:\716000 ( Direct Cost: \716000 )
現在、日本全国の放置里山林が深刻な課題となっている。特に、河川上流域の過疎高齢化が急速に進む集落では放置里山林の増加が著しい。
そこで本研究事業では、大分県国東半島地域を中心にした世界農業遺産の環境において、薬草および薬木を調査し、その効能、使用方法などについての図鑑を作成することを目的とする。 -
一乗朝倉氏遺跡の山林部・山裾部の景観改善ー諏訪館跡庭園の背景林の広葉樹林化
2023.06
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 特別史跡 The General Consignment Study
上原 巌
福井県の特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡では、山林部・山裾部の景観改善を目的に、特別名勝指定の庭園の背景となっている現在のスギ人工林を広葉樹林化していくことを計画している。
そこで、本研究では、現地踏査と調査をおこない、
①スギ林の伐採手法
②広葉樹への更新手法
の2点を検討し、実施する。 -
森の香り体験 東京農業大学教授と楽しむ樹の香り森の香り ~森の香り散策と手作りアロマ・ウォーター体験~
2022.10
国立青少年教育振興機構 一般受託研究:東京農業大学 総合研究所 The General Consignment Study
Presentations 【 display / non-display 】
-
上原 巌
2025年度 東京農大 東日本支援プロジェクト ならびに 東京農大:復興から地域創生への農林業支援プロジェクト 2025年度 活動報告会 2026.01 東京農業大学
Event date: 2026.01
Venue:福島県相馬市 JAふくしま未来 相馬中村営農センター
1.はじめに 相馬地方の放置林での間伐による植生再生
東京農業大学・東日本支援プロジェクトでは、2019年から相馬地方森林組合に作業委託をし、各地の私有林において間伐を実施してきた。2019年10月は相馬市今田地区のスギ林(36年生:立木密度3000本/ha、平均樹高11m、平均DBH 20㎝)、2020年12月には南相馬市原町区のヒノキ林(32年生:立木密度3500本/ha、平均樹高12m、平均DBH 15㎝)、2021年12月には相馬市玉野地区のコナラ、クリ等を主林木とする広葉樹二次林(立木密度3500本/ha、平均樹高17m、平均DBH 25㎝)、2022年12月には南相馬市小高区のヒノキ若齢林(約20年生:立木密度2000本/ha、平均樹高8m、平均DBH 14cm)において、それぞれ50%の強度間伐を実施した。間伐をおこなった結果、各林分の相対照度は向上し、新生の樹木の実生が確認されてきている。
そこで、本年度は、ここまでの間伐の成果をまとめるために、広葉樹二次林と2か所のヒノキ林において、福島県内の森林・林業関係者による現地研修会を実施するはこびとなった。
2.現地研修会の実施
現地研修会は、福島県森林組合連合会を通して9月より参加者を公募し、10月15日(水)に実施した。
研修会の参加者は、福島県森林組合連合会、相馬地方森林組合、地元の山林所有者の方をはじめ、南会津の木材生産者、いわき市の山林所有者などであった。
当日は、朝10時にJR福島駅前に集合し、乗用車に分乗して現地に向かった。午前から順番に、相馬市玉野地区の広葉樹林二次林(2021年に間伐実施)、南相馬市小高区の20年生のヒノキ林(2020年に間伐実施)、南相馬市原町区の20年生のヒノキ林(2022年に間伐実施)の3つの林分を踏査し(写真2)、18時半にJR福島駅で解散した。
現地研修会では、各林分の植生回復状況なども踏査したが、最も林床植生が繁茂したのは、広葉樹二次林であった。コナラ、クヌギ、モミなどの高木層の下に、50種以上の樹木の実生が確認された。次に若齢のヒノキ林では40種ほどの樹木の芽生えが見られ、その繁茂状況も旺盛であった(写真3)。漏脂病や徳利病などの病害も見られず、順調な成育がうかがえている。
研修会では、下記の事柄についても山林所有者の方からお聞きした。
①今から60~70年前は、上流からの水の便が良く、あちこちに水田を作ったが、震災後、稲作をやめてしまった農家が多い
②山林は地域の共有地であり、適地適木で分割されたものの、今ではその境界があいまいになってしまっている
③浜通り地方では、林木の年輪の目が細かいことから、かつては船材も生産していた。
④丸太は、馬や木馬を使って搬出をしていた
⑤現在では山主であっても、林床の樹木、植物がわからない
いずれもお聞きして有意義なことばかりであったが、山林における水利やかつての搬出の形態、また、造林種や、浜通りにおける立木の生育特性などについてもこれまで知らなかった知見を得ることができた。また、林床の樹種名がわからないとのことから、今後は、林地における樹木名の実地講習会もおこなうことが起案された。
福島県浜通り地方に限らず、とかく閉塞感、先行き不透明感のある森林・林業界であるが、間伐後に一斉に芽生えた植生のように、新たな希望を引き続き見つけていきたい。
3.今後の森林施業
スギ、ヒノキ林では、今後さらに追加間伐が必要であると思われる。とりわけヒノキ林の場合は、日光を遮る独特の樹冠が形成されるため、単純な本数による間伐率よりも、実際の林冠、樹冠の適正な配置による密度コントロールの方が重要である。当面は、この間伐の実施によって、林冠および林間の空間を開け、風散布、鳥散布などを、また埋土種子の発芽を促していくことが得策であると考える。植生的には、クリ、コナラ、ミズナラなどのブナ科をはじめ、ホオノキ、コブシ、カエデ類などの有用広葉樹が数多くみられており、貴重種のメグスリノキやクロモジなどの薬木もみられることから、これらの有用広葉樹の育成にも力点を注いでいくことが望まれる。林床に発現したこれらの実生の育成をおこない、針広混交林の造成とともに、林床植生の有効活用をはかることも今後の課題である。
4.訪問型農学スクールの実施
本年度は、相馬高校(7月)、相馬農業高校(11月)、原町高校(12月)の3校を訪問し、各学校において身近な樹木の観察、自然に中にみられる数学的要素、そして学校周辺で採集した樹木の枝葉から芳香水の製作をおこなった。 -
上原 巌
東京農大 オープンカレッジ 2025後期 2025.12 東京農業大学
Event date: 2025.12
Language:Japanese Presentation type:Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech
Venue:東京農業大学 世田谷キャンパス 国際センター
室内、屋外を問わず、私たちの世界(自然界)には数学がたくさん存在しています。例えば、落葉広葉樹の樹形をはじめ、スギ、ヒノキなどの枝葉、シダ植物、海岸線、霜の形、植物の根系、血管・神経系、菌の形態に至るまで、自然界の様々な形には、自己相似の形のくりかえしがみられます。
本講座では、自然界における様々な事象を数学的にご紹介します。対称形、円周率、フラクタル(自己相似形)などをぜひ一緒に見つけてみましょう。この講座で、前よりももっと数学が身近に感じられるようになるはずです。 -
Iwao UEHARA
2025.10
Event date: 2025.10
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (general)
Country:Japan
Fuji City, Shizuoka Prefecture, has a forest coverage rate of 50%, of which 80% is Japanese cypress (Chamaecyparis obtusa) forest. Aiming to brand "Fuji Hinoki," the city produces logs ranging from grades A to D, and continues to plant hinoki trees.
This study reports the results of a survey of the stand conditions in a young hinoki forest in Fuji City. The subject of the survey was a 19-year-old hinoki forest planted in the Obuchi-aza-Marubi district of Fuji City, Shizuoka Prefecture, at an altitude of approximately 850 m, on black soil with lava flows from Mount Fuji as its bedrock. In 2006, the forest was planted at a density of 4,000 trees per hectare, with a ratio of 90% hinoki and 10% zelkova. The forest covers an area of 3.39 hectares, and 20% of the hinoki trees were thinned in 2022. By this time, almost no zelkova trees were found. Pruning has not been carried out since planting.
In this study, ten 10m x 10m quadrats were established within the forest compartment. In addition to conducting individual tree surveys, the height of the trunk branching points (such as forks and trifurcations) from ground level, as well as the height and length of furrow rot areas, were measured for each standing tree within each quadrat. Furthermore, one sample tree was selected from each quadrat, and its branching point was cross-sectioned for growth analysis. Measurements of the pH and humidity of the forest soil were also conducted within each quadrat.
The survey results indicated that the incidence of forks (such as forks and trifurcations) was approximately 49%. Furthermore, furrow rot, likely caused by deer antler sharpening, was observed in 13% of the standing trees, and a tokkuri-shaped trunk shape was observed in 14% of the standing trees. Two main causes of forks were considered: damage due to weather damage and animal feeding on the apical buds. However, cross-sectional surveys of forks indicated that damage by animals such as deer was the most likely cause.
Keywords: fork, sharpening horn, groove rot, sake bottle shape, wild animals -
Forest Therapy (Shinrin-ryoho 森林療癒) and Its Possibility in China Invited International conference
Jiangsu Academy of Agricultural Sciences Fallow Agricultural Research Institute Training Session 2025.09 Jiangsu Academy of Agricultural Sciences Fallow Agricultural Research Institute Training Session
Event date: 2025.09
Language:English Presentation type:Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech
Venue:Online Country:China
1. What is Forest Therapy and its Healing Effects?
Forest Therapy (Shinrin-ryoho) is promoting the health of both of forests and human beings! Forests and the trees within them have many healing properties. They promote our health, prevent illness, provide relaxation opportunities, and a rehabilitation environment, can be a treatment place for disabilities, peaceful counseling space, and so forth. When we arrive in the forest, we sometimes pay more attention to oneself and one’s life. Walking and exercise in the forest also change our attitudes and perspectives. Trees also have many fascinating aspects for medical, art, and care utilization. However, some forests have been ill, depressed, and having stress like us human beings. So, forest therapy is attempting to heal forest and human beings each other.
2. Examples of Forest Therapy and Forest Amenity Programs
There have been many examples of forest therapy and forest amenity programs in Japan.
First of all, Forest Walking. Walking is the simplest rehabilitation method and whole body exercise. Walking can prevent lifestyle related disease. In addition, individuals walking in the forest enjoy the landscape, fresh air, and natural environment.
Next, relaxation. It is quiet and peaceful in the forest. Relaxation in the forest inspires natural peace in our body and mind. It adjusts our nervous system balance, too.
Third, rehabilitation. For clients after an operation, accident, and preparing to reintegrate with society, forest walking & working is one possible rehabilitation program.
Fourth, treatment and occupational activities in the forest. Carrying logs & branches, cutting trees & weeds, and planting trees are typical examples of occupational therapy.
Fifth, counseling. Counseling in the forest makes clients relax and sensitive. Forest amenities like landscape aesthetics, wind, fragrance, birds singing sometimes give useful hints to solve our problems and provide an ideal setting for traditional counseling approaches.
I hope you will design your own healing or health promoting programs using forests and trees as a setting and as inspiration by my presentation
3. Case Studies of Forest Amenities
There have been already many invaluable case studies utilizing forest amenities in Japan.
By experiencing forest activities for a long term and constantly, some clients with mental, psychological, and physical disabilities showed positive treatment effects! Their communication has been also changed positively. Some experimental studies suggest that forest walking can reduce stress hormone, enhance immune function, and balance nervous system. Recently, some case studies of the patients with Dementia could recover their communication ability, too.
Trees also have great possibilities for healing. For example, some trees provide medicine, herb tea, and fragrance which have certain healing effects.
In addition, trees and forest have been sometimes worshipped as natural god in Japanese culture.
4. Possibilities of Forest and Tree Amenities in China
What is the special character of people living in China and how does it differ from Japan and other parts of the world? Many people prefer to enjoy and exercise in the park and nature. There are beautiful green parks, mountains, and forests in the China. Also, many invaluable kinds of trees have been in natural and various local forests. Therefore, Chinese forest environment has a big potential for forest therapy program. Let’s reconsider your Chinese forests in this context and develop these possibilities together! -
上原 巌
日本カウンセリング学会 第57回大会 2025.08 日本カウンセリング学会
Event date: 2025.08
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (general)
Venue:江戸川大学 Country:Japan
カウンセリングをはじめ、日常的なコミュニケーション、人間関係では様々なアプローチがおこなわれている。その中に「支持的」という姿勢と言葉がある。これは、クライエントの主訴、思いだけでなく、クライエントの存在そのものを肯定的に支えていく意味合いも持っている。
そこで本研究では、学生指導の上で、支持的な姿勢をこころみた二つの事例を報告した。それぞれのクライエントには支持的な姿勢で指導を同様にこころみたが、それぞれ異なる結果となった。個々のクライエントの成長過程やパーソナリティ、それぞれの要望点を常に整理、ふまえながら、指導法を適宜アレンジしていく姿勢の重要性も再認識された。
Symposium 【 display / non-display 】
-
浜通り地方における間伐林研修会
福島県森林組合連合会、相馬地方森林組合、山林所有者、木材生産業者など
福島県相馬市、南相馬市 2025.10 - 2025.10
東京農業大学・東日本支援プロジェクトでは、2011年より、福島県相馬地方の森林再生に取り組んできた。2019~2022年までは、福島イノベーションコースト事業の助成によって、相馬市、南相馬市の山林において、相馬地方森林組合に間伐を実施していただいた。
本研修会では、そのうちの3か所の間伐林(広葉樹二次林、2つのヒノキ林)を紹介し、意見交換をおこなった。 -
国際森林療法実践研修会
江蘇省農業科学院休閑農業研究所、江蘇省農業科学院農業景観文化団体
江蘇省南京遊子山休閑旅遊区 2025.09 - 2025.09
江蘇省の南京遊子山(標高約180m)にて、森林療法の実地研修会をおこない、今後の可能性についても会議をおこなった。
今後、東京農業大学との研究の連携を強く希望された。 -
南京紫金山国家森林公園調査研究交流会
江蘇省農業科学院休閑農業研究所、江蘇省、日本江蘇省商工会
南京紫金山国家森林公園 2025.09 - 2025.09
江蘇省農業科学院休閑農業研究所の職員のみなさまをはじめ、江蘇省の方々と森林を活用した健康増進について自由に会議をおこなった
-
障がい者・高齢者の森林空間利用の事例 ~高齢者介護・障がい者福祉施設、特別支援学級の事例報告~
公開セミナー「ぼちぼち森林に行ってみませんか! ~障がい者・高齢者のための森林空間利用最前線 ~」
ミーティングスペースAP西新宿 ,およびウェブ開催 2025.05 - 2025.05
①地域病院での事例(福岡県)
②社会福祉施設の活動事例(福岡県)
③社会福祉施設の活動事例(東京都、埼玉県)
④小学校の事例(関東の小学校)
各地での現状と課題
今後の可能性、方向性
を報告した。 -
International Forest Therapy Forum
International Forest Therapy Forum attendee
Taipei Forestry and Nature Conservation Agency 2024.12 - 2024.12
Discussing the effects of forest therapy and pussibilities in the future. I reported the case studies in Japan.
Teaching Experience 【 display / non-display 】
-
「ふしぎ発見! 植物のカタチとカオリを研究してみよう」 夏休み探求フェスタ2025 in 東京農業大学
2025.08 Institution:Tokyo University of Agriculture
Level:Other Country:Japan
わたしたちの身近にある植物。実は、その植物には様々な不思議があります!たとえば、香り、どの植物にも香りがあり、お薬やシャンプーにもその香りは使われています。そして、植物は不思議な数学の世界も持っているのです。
そんな植物の不思議を一緒に学びます。 -
農大出張講義
-
信州クラーク塾 講師 2020年〜
-
福島 高校生 サマースクール、オータムスクール (東京農業大学 東日本支援プロジェクト)
-
農大出前講座
Committee Memberships 【 display / non-display 】
-
日本森林学会 中等教育連絡推進委員
2024.05 - 2025.10
Committee type:Academic society
-
日本森林学会 第135回大会プログラム編成委員会
2023.06 - 2024.05
Committee type:Academic society
-
関東森林学会 編集担当理事、関東森林研究編集委員長
2019.04 - 2021.09
Committee type:Academic society
関東森林研究第71巻1号2号
関東森林研究第72巻1号2号
の編集を担当した。 -
日本森林保健学会 理事長
2010.04
Committee type:Academic society
Social Activities 【 display / non-display 】
-
金沢市林業大学校 非常勤講師
Role(s): Lecturer
金沢市 2024.04
Audience: General
Type:Research consultation
-
Role(s): Logistic support
東京都立豊多摩高等学校 東京都立豊多摩高等学校 2023.04
Audience: High school students, Guardians, General, Governmental agency
Type:Research consultation
-
Consultant of Green Therapy and Landscape Architecture Research Center of Tsinghua University, China
Role(s): Consultant
Tsinghua University, China Beijing, China 2019.09 - 2022.08
Audience: College students, Graduate students, Teachers, Researchesrs, General, Scientific
Type:Research consultation
-
木原営林大和事業財団 理事
木原営林大和事業財団 2019.04
Type:Research consultation
-
みえ森林・林業アカデミー 非常勤講師
Role(s): Lecturer
三重県 2019.04
Academic Activities 【 display / non-display 】
-
青梅の森運営協議会委員
青梅市 2017.04
Type:academic_research
Basic stance of industry-university cooperation 【 display / non-display 】
-
地域の森林資源を大切に保育管理しながら、森林環境の持つ多面的効用がより発揮できるような手法を考察していきたい。特に全国各地の「放置林」の再生手法に力を注ぎたい。
Attractiveness of Research 【 display / non-display 】
-
身近な自然環境に興味を持ちながら、自分自身も見つめてみていってください。
東京農業大学には多様な選択肢があります。