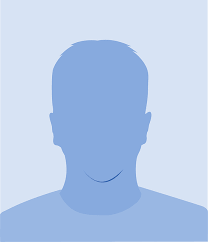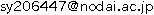|
職名 |
教授 |
|
研究室住所 |
神奈川県厚木市船子1737 |
|
連絡先 |
|
|
外部リンク |
|
|
山田 晋 (ヤマダ ススム) YAMADA Susumu 教授 |
学内職務経歴 【 表示 / 非表示 】
-
東京農業大学 農学部 生物資源開発学科 准教授
2018年04月 - 2021年03月
-
東京農業大学 農学部 生物資源開発学科 教授
2021年04月 - 現在
所属学協会 【 表示 / 非表示 】
-
厚木市環境審議会
2021年09月 - 2023年03月
-
川崎市橘樹官衙遺跡群調査整備委員会・委員
2021年04月 - 現在
-
田島ケ原サクラソウ自生地自然科学分析等緊急調査検討会・委員
2020年04月 - 現在
-
日本緑化工学会
2010年04月 - 現在
-
日本雑草学会
2007年04月 - 現在
論文 【 表示 / 非表示 】
-
Yamada S, Yoshida W, Iida M, Kitagawa Y, Mitchley J
PeerJ 12:e17487 2024年06月
-
丘陵地の谷部において水田とその周辺湿地の土に眠る種子 招待あり
山田 晋, 中山 恵都子
植調 59 ( 9 ) 1 - 5 2025年12月
担当区分:筆頭著者 記述言語:日本語 出版者・発行元:日本植物調整剤研究協会
-
田島ケ原サクラソウ自生地における3年間のチューブ灌水が植生に及ぼす影響 査読あり
山本暁生・山田 晋・島守涼太・大田一輝・重川勇気・荒木祐二
日本緑化工学会誌 51 ( 2 ) 241 - 246 2025年10月
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:日本緑化工学会
-
陣場山山頂に植栽したアキノキリンソウおよびコオニユリの当年性苗の3年間の生育状況 査読あり
山田 晋, 濱田 耕太郎, 伊藤 在由, 川口 征也, 丸山 元
日本緑化工学会誌 51 ( 1 ) 25 - 30 2025年08月
担当区分:筆頭著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:日本緑化工学会
<p>半自然草地の復元創出を試みる際,生育地から消えた植物種を積極的に導入する手法の開発は重要である。本研究では,現地採取した種子から育苗したアキノキリンソウとコオニユリの当年生苗各40苗を,2021年に陣場山山頂の裸地と既存草地に植栽した。定着状況を2023年まで追跡し,半自然草地の復元に関する知見を得ることとした。2023年の苗の残存率は,アキノキリンソウで約80%,コオニユリで約60%だった。植栽個体は周辺植生から被陰を受けており,より光要求性の低いアキノキリンソウの残存率がより高くなったと考えられた。裸地に植栽を行った区画では2023年にコオニユリの残存率がとくに低下し,その原因としてメマツヨイグサの優占化が考えられた。</p>
DOI: 10.7211/jjsrt.51.25
-
石毛 茉希, 橋川 慧, 山田 晋
日本緑化工学会誌 51 ( 1 ) 163 - 166 2025年08月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:日本緑化工学会
<p>丘陵地における微地形や植生管理の違いは,土壌動物生息状況に影響しうるが,その影響の程度については明らかでない。そこで多摩丘陵に位置する東京都町田市内の落葉広葉樹二次林において,異なる微地形と植生管理を組み合わせた7条件で土壌を採取し,ツルグレン装置にて土壌動物を抽出した。結果,土壌動物群数と個体数に関して,微地形条件間で有意差はなかったが,ナガミミズ目が谷頭部に偏在した。植生管理に関しては,秋季の動物群数が無管理で有意に多く確認され,そこではダニ目が偏在した。微地形の違いに起因する水分条件の差異,植生管理の違いに起因するリターの堆積量の差異が,土壌動物相に大きな影響を及ぼしていると示唆された。</p>
DOI: 10.7211/jjsrt.51.163
書籍等出版物 【 表示 / 非表示 】
-
生態工学
亀山章・倉本宣・佐伯いく代( 担当: 共著)
朝倉書店 2021年09月
記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
根本 正之, 山田 晋, 田淵 誠也( 担当: 共著)
朝倉書店 2020年05月 ( ISBN:9784254420425 )
記述言語:日本語 著書種別:一般書・啓蒙書
-
身近な雑草の生物学
根本正之・冨永達・山田晋ら( 担当: 共著 , 範囲: 4.3章「雑草群落の利用と保全」)
朝倉書店 2014年03月
担当ページ:pp. 103-114, 151 記述言語:日本語 著書種別:教科書・概説・概論
作物と雑草との共存という観点から,耕地生態系において緑肥や生態系機能向上のために雑草を利用する試みや,耕地の生物多様性を維持する観点から雑草を保全する取り組みについて,研究論文のレビューを通して紹介した。
-
身近な自然の保全生態学
根本正之・高槻成紀・山田晋・冨永達・三浦励一・渡辺守・平舘俊太郎・楠本良延・吉武啓・馬場友希・浅川晋・村瀬潤( 担当: 共著 , 範囲: 3章「里山と谷津田の生物多様性」)
培風館 2010年09月
担当ページ:pp. 49-58, 213 記述言語:日本語 著書種別:教科書・概説・概論
日本の里地里山の代表的形態である里山および谷津田という2つの土地利用を例に,農村地域の植物多様性や,その生物多様性をもたらす要因について紹介した。
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
粗放管理時代における河川堤防の実用的な生態緑化・植生管理手法の開発
2025年04月 - 現在
科学研究費補助金 科学研究費補助金基盤(C)
担当区分:研究代表者
-
UAV三次元情報を用いた草地性絶滅危惧種カヤネズミの営巣環境解析手法の開発
2025年04月 - 現在
文部科学省 科学研究費補助金 科学研究費補助金基盤(C)
三浦直子・山田晋
担当区分:研究分担者
-
粗放管理時代における河川堤防の合理的な植生管理・生態緑化手法の開発
2020年04月 - 2024年03月
科学研究費補助金 基盤研究(B)
山田晋
-
多様な在来種が生育する草地植生は河川堤防法面に創出可能か?
2017年04月 - 2020年03月
科学研究費補助金 基盤研究(B)
山田晋
担当区分:研究代表者
-
北東アジアの砂漠化地域における生態系サービス再生を促進する植生修復技術の開発
2015年04月 - 2018年03月
科学研究費補助金 基盤研究(B)
大黒俊哉
担当区分:研究分担者
その他競争的資金獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
複数の在来植物種を利用した混植植栽によるチガヤ堤創出手法の開発
2025年04月 - 2027年03月
河川財団 河川基金
山田晋・松嶋賢一
担当区分:研究代表者
配分額:1500000円 ( 直接経費:1500000円 )
-
チガヤ堤の安定的形成に資するチガヤ苗の植栽・管理手法の開発:植物の自他識別能力の活用
2020年04月 - 2022年03月
民間財団等 河川基金
山田晋
資金種別:競争的資金
-
堤防緑化施工地における帰化植物セイバンモロコシの発芽・定着メカニズムの解明
2017年04月 - 2019年03月
民間財団等 河川基金
山田晋
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
-
河川堤防に生育する帰化植物セイバンモロコシの蔓延防止に向けた発芽・生育特性の解明
2015年04月 - 2017年03月
民間財団等 河川基金
山田晋
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
-
東アジアモンスーン地域において持続的な物質循環を目指した農地生態系の研究
2010年04月 - 2011年03月
民間財団等 住友財団
加藤洋一郎
資金種別:競争的資金
受託研究受入実績 【 表示 / 非表示 】
-
法面緑化評価技術開発
2021年04月 - 現在
鹿島建設株式会社 一般受託研究
-
堤防管理に適した植生が成立する築堤土壌特性の解明
2015年04月 - 2016年03月
河川財団 一般受託研究 一般受託研究
山田晋
担当区分:研究分担者
委員歴 【 表示 / 非表示 】
-
日本緑化工学会 評議員
2025年11月 - 2027年09月
団体区分:学協会
-
エディタ
2024年04月 - 現在
団体区分:学協会
-
日本雑草学会 英文誌編集委員会・委員
2024年04月 - 現在
団体区分:学協会
-
日本緑化工学会 論文編集委員
2024年02月 - 現在
団体区分:学協会
-
東京都 環境審議会
2023年04月 - 現在
団体区分:自治体
メディア報道 【 表示 / 非表示 】
-
生物多様性を守るために イギリスの対策に学ぶ 新聞・雑誌
聖教新聞 2024年07月
執筆者:本人
-
改修された荒川堤防に在来種を呼び戻すためにすべきこと 新聞・雑誌
埼玉新聞 2019年12月
執筆者:本人
研究の魅力 【 表示 / 非表示 】
-
生態学を道具に,身近な自然環境の不思議や疑問を解き明かしていきたいと思っています。野外調査から何か新しいことを発見したときのワクワクを多くの人に知ってもらえるよう、教育研究活動に取り組んでいます。